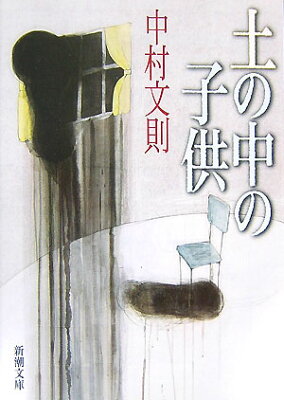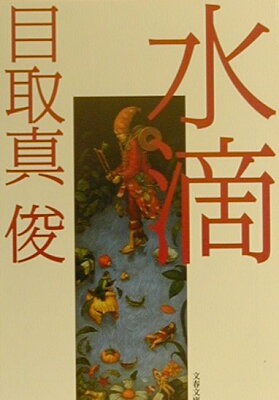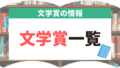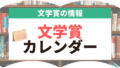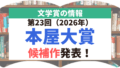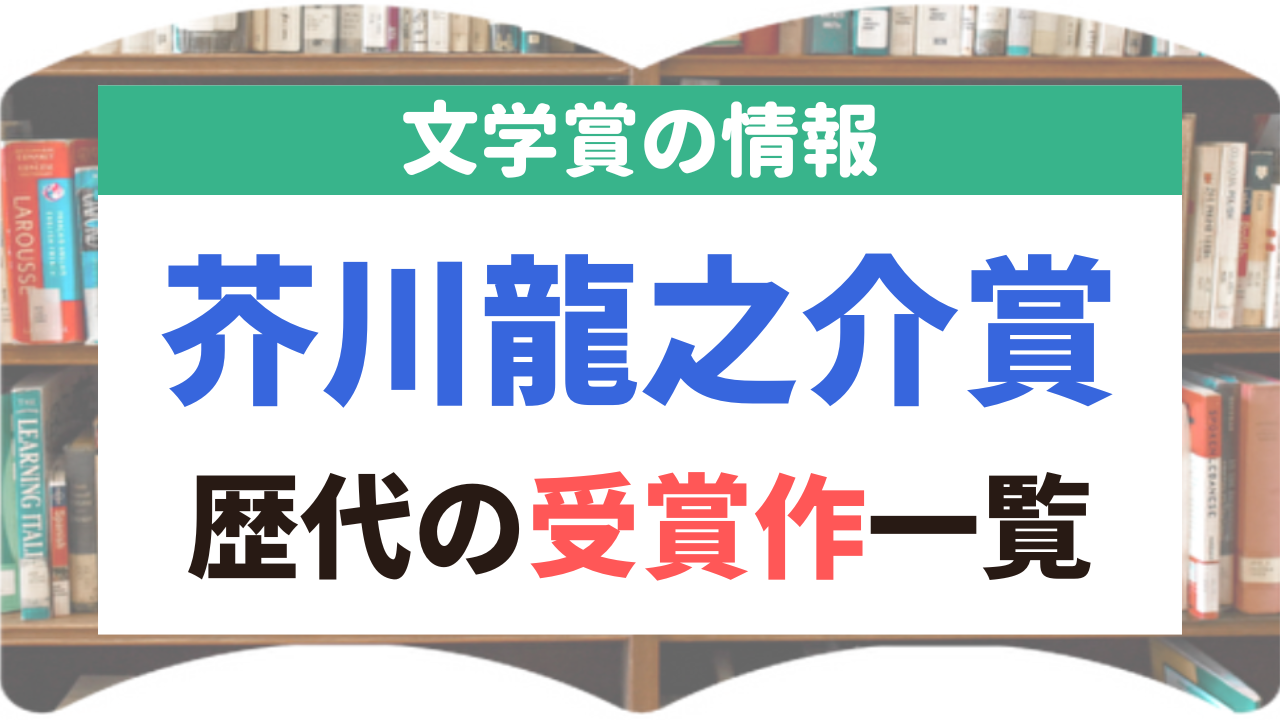
芥川龍之介賞(あくたがわりゅうのすけしょう)とは、大正時代を代表する小説家の一人・芥川龍之介の業績を記念して、友人であり「文藝春秋」を創刊者でもあった菊池寛が創設した文学賞です。芥川は「文藝春秋」創刊号から巻頭随筆「侏儒の言葉」を連載。創刊10周年の「文藝春秋」執筆回数番付では「東(張出)横綱」に名前が上がるほどでしたが、昭和2年に致死量の睡眠薬を飲み、35歳の若さでこの世を去ります。友人の死を悲しんだ菊池寛は、「文藝春秋」昭和10年1月号で、芥川龍之介賞の制定を宣言しました。第1回受賞作に石川達三の「蒼氓」が選ばれ、以来、芥川賞は無名・新人の純文学作品に授与されることになりました。候補作は上半期は前年の12月からその年の5月に発表された作品、下半期は6月から11月の間に発表された作品から選出され、選考会は上半期は7月中旬、下半期は1月中旬に行なわれます。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賞名 | 芥川龍之介賞 |
| 設立年 | 1935年 |
| 選考頻度 | 上半期(12-5月発表作品対象)(7月発表)、下半期(6-11月発表作品対象)(1月発表) |
| 運営団体 | 文藝春秋 |
受賞者一覧
「Kindleで読み放題」 および 「オーディブルで聴ける」 対象作品は時期によって変わる場合がございます。

第173回(2025) 上
受賞作なし

第145回(2011) 上
受賞作なし

第142回(2009) 下
受賞作なし

第121回(1999) 上
受賞作なし

第118回(1997) 下
受賞作なし

第112回(1994) 下
受賞作なし

第101回(1989) 上
受賞作なし

第96回(1986) 下
受賞作なし

第95回(1986) 上
受賞作なし

第93回(1985) 上
受賞作なし

第91回(1984) 上
受賞作なし

第89回(1983) 上
受賞作なし

第87回(1982) 上
受賞作なし

第86回(1981) 下
受賞作なし

第83回(1980) 上
受賞作なし

第81回(1979) 上
愚者の夜
青野聰

第80回(1978) 下
受賞作なし

第78回(1977) 下
榧の木祭り
高城修三

第76回(1976) 下
受賞作なし

第71回(1974) 上
受賞作なし

第67回(1972) 上
誰かが触った
宮原昭夫

第65回(1971) 上
受賞作なし

第60回(1968) 下
受賞作なし

第55回(1966) 上
受賞作なし

第52回(1964) 下
受賞作なし

第49回(1963) 上
少年の橋
後藤紀一

第48回(1962) 下
受賞作なし

第47回(1962) 上
美談の出発
川村晃

第45回(1961) 上
受賞作なし

第42回(1959) 下
受賞作なし

第41回(1959) 上
山塔
斯波四郎

第40回(1958) 下
受賞作なし

第36回(1956) 下
受賞作なし

第35回(1956) 上
海人舟
近藤啓太郎

第30回(1953) 下
受賞作なし

第27回(1952) 上
受賞作なし

第25回(1951) 上
春の草
石川利光

第24回(1950) 下
受賞作なし

第23回(1950) 上
異邦人
辻亮一

第21回(1949) 上
本の話
由起しげ子

第21回(1949) 上
確証
小谷剛

第20回(1944) 下
雁立
清水基吉

第19回(1944) 上
登攀
小尾十三

第17回(1943) 上
纏足の頃
石塚喜久三

第16回(1942) 下
連絡員
倉光俊夫

第15回(1942) 上
受賞作なし

第14回(1941) 下
青果の市
芝木好子

第13回(1941) 上
長江デルタ
多田裕計

第12回(1940) 下
平賀源内
櫻田常久

第11回(1940) 上
受賞作なし

第10回(1939) 下
密獵者
寒川光太郎

第9回(1939) 上
鶏騒動
半田義之

第8回(1938) 下
乗合馬車
中里恒子

第7回(1938) 上
厚物咲
中山義秀

第4回(1936) 下
地中海
冨澤有爲男

第3回(1936) 上
城外
小田嶽夫

第2回(1935) 下
受賞作なし