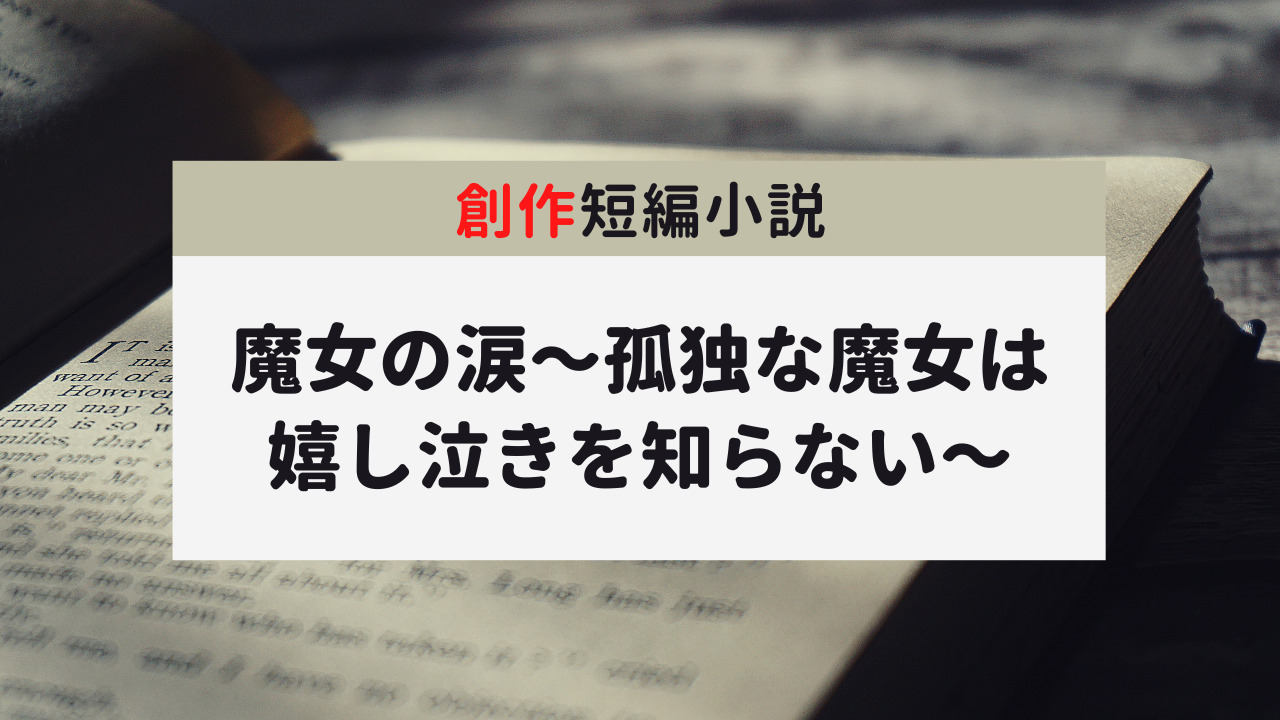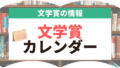1
暖かい日でした。
太陽はサンサンと輝き、生温くも冷たくもない心地よい風が吹いていました。こんな日は、外に出て、森の土の匂いを嗅かぎながら、小鳥のさえずりを聞きながら、空がまっかに染まるまでお気に入りの本を読むのが、ソーニャの常でした。
シルバーホワイトの長い髪を後ろで一つに三つ編みし、一張羅のスカイブルーのワンピースに着替えたソーニャは寝室から出ました。
本を楽しむ前に、ソーニャにはいくつかやることがあります。パンを焼き、スープを煮て、さらに、それらができあがる間に掃き掃除と洗濯をするのです。
これはソーニャの日課でした。森の中の小さな家に一人で暮らすソーニャにとって、それらは一日たりともサボれないことでした。
だって他にやってくれる人はいませんから。
慣れた手つきで、夜の間に発酵させておいたタネを捏ね、温めたオーブンに入れます。野菜と少しのお肉を切り、お鍋に放り込みます。今日は、トマトがたくさんあるのでトマトスープです。鍋を弱火にかけ、さっと掃き掃除をすませました。毎日しているので、ほこりもあまり溜まっていません。そうして、鍋の中身がまだ揺れていないことを確認すると、洗濯板・石鹸・洗濯物の入った木のカゴを持って外に出ます。洗濯はいつも外にある水道でしていました。
だって洗ってすぐ干せますから。
カゴを水道の下に置き、蛇口を捻ろうとしたその時、ソーニャの後ろから、女性の声がしました。
「もし。貴女が、魔女のソーニャさんですか」
ソーニャは振り返ると、そのジェイド色の瞳に、フードを目深に被った女性の姿を映しました。
「そうです」
ソーニャがそう答えると、女性は勢いよくソーニャに詰め寄りました。走ったせいか、フードは落ち、女性の姿が明らかになりました。ゴールドの髪にブルーの瞳。ここアルカンドラ王国でもっとも一般的な組み合わせでした。
けれども、女性の様子は決して普通ではありません。
目の下にくろいくろいクマを作り、頬は痩せこけていました。歯をカチカチ言わせながら震えています。
しかしながら、ソーニャは少しも動揺していませんでした。なぜなら、ソーニャを訪ねてくる人々は、みな同じような形相だったからです。
「どうしました」
ソーニャは、答えが分かっていながらも、努めて優しい声で尋ねました。
すると女性は、ソーニャの両腕を震える手でガッチリと掴みながら、訴えました。
「ああ……どうか、どうか『魔女の涙』をお譲りください! む、息子が病なのです。もう、街の医者にも隣街の医者にも王都の医者にも匙を投げられました!! もう貴女しか頼る方がいないのです……! どうか、どうか……」
何度も頭を下げる女の肩を優しく撫でた後、ソーニャは言いました。
「少しだけ、待っていてください」
ソーニャは、急いで家の中へと戻ります。
食卓の横の棚から、小さな瓶を手に取りました。
そして、それを顔の下に当てると、今まで悲しかったこと・辛かったことを思い出します。
一人で耐えた嵐の夜。
静まり返った冬の朝。
魔女を理由にいじめられた幼少期。
そして、お母さんを亡くしたあの日
あっという間にソーニャの頬は、塩辛い涙で濡れていました。それらを落とさぬよう、丁寧に小瓶に貯めていきます。
これも、家事と同じく慣れたものでした。
煮立った鍋の火を止めたあと、ソーニャは再び家の外へ出ました。
外では、自分を抱きしめるようにして立つ女性の姿がありました。
ソーニャはそっと女性に近付くと、小瓶を差し出しました。
「どうぞ」
うつむく女性は、その小瓶に気が付き、パッと顔を上げます。
ブルーの目が大きく見開かれ、揺れていました。
女性は、何度もお礼を告げてから、大急ぎで帰っていきました。
それを見送ったソーニャは、途中止めになっていた洗濯を再開させました。
2
大陸の西、国境の半分が海に面した小国・アルカンドラ王国には、とある噂がありました。
『魔女の涙は、百薬の長
どんな病も、たちどころに治る』
ある人にとっては、絵空事。
ある人にとっては、最後の頼みの綱。
そして、ある人にとっては、とても興味を惹かれることでありました。
◆◆◆
森の入り口に、真っ黒いローブで頭から足の先まで覆った人影がありました。
唯一ローブから覗いているのは、これまた真っ黒な細身のブーツだけ。
これでは、男性なのか女性なのかすら分かりません。
分かるのは、子どもじゃない。そのくらいです。
ローブの人は、木々の生い茂る森の中に足を踏み入れました。
少しすると、前方から女性が走ってきました。顔色は悪いのに、そのブルーの瞳には光が満ちていました。
女性は、大事そうに、胸に小瓶を抱えていました。
「ふむ」
女性が、自分の来た方へ走り去っていくのを見ていたローブの人は、呟きました。その声は、低い、けれども澄んだ男性の声でした。
ローブの青年は、森の奥へと足を進めました。
踏みしめられた道を進んでいくと、一軒の小さな家が見えました。木造の家からは、オレンジ色の明かりが漏れています。
青年は、家の扉を叩きました。
トントン
けれども、応答はありません。
青年は、家の裏に回ってみることにしました。
家の側面を歩いていると、なにやら可愛らしい声が聞こえてきました。
どうやら歌声のようです。
青年は、少し早足で家の裏へと向かいました。
そこには、本を片手に小鳥たちと戯れる少女の姿がありました。シルバーホワイトのお下げ髪が、右に左に揺れていました。
軽やかなステップで踊っていた少女は、ふいに青年の方を向きました。
「あら」
ようやく青年の存在に気がついた少女は、途端に踊るのを止めてしまいました。
青年は、もう少し隠れていればよかったと後悔をしました。
美しい少女の歌声は、とても耳ごごちのいいものだったからです。
「わたしにご用ですか」
少女は、本を小さな机に置き、青年に近づいてきました。
「ええ。あなたが魔女のソーニャさん、ですよね」
男の問いかけに少女・ソーニャは頷ずきました。
しかし、それと同時にソーニャは首を傾げていました。
いつものお客さまとは、少し違う気がしたからです。
顔を隠しているのは、いつものことです。
ソーニャに名を尋ねるのも、いつものことです
けれども、声が違いました。いつもは、震えて切羽詰まった声なのに、この目の前の人の声は、生き生きとしているのです。
例を見ないことに、ソーニャは身を固くしました。
ジェイドの瞳からの視線が厳しくなるのを感じたのでしょうか。
青年は慌ててローブを脱ぎました。
「怪しいものではありません」
ソーニャは息をのみました。
青年の顔がたいそう美しかったから、それもあります。けれどもそれ以上に、彼のアッシュブロンドの瞳とワインレッドの髪に驚いたのです。その組み合わせは、アルカンドラ王家を象徴するものでした。
世間に疎いソーニャでも、彼の正体が分かってしまいました。
「あ、貴方さまは……」
「申し遅れました。アルカンドラ王国 第二王子 フレン・ナシャータ・エルカ・アルカンドラです。どうぞフレンとお呼びください。ソーニャ」
胸に手を当て、恭しく頭を下げる彼は、まさしく王子さまでした。
「フレン……さま。今日はどのようなご用件で? 王家の方がご病気になられたのですか」
とても王子さまを呼び捨てにできなかったソーニャは、そっと敬称を付けて呼びました。
青年・フレンは、少し不満げでしたが、何も文句は言いませんでした。
代わりに、自分が訪ねてきたわけを話しました。
「王家の者はみな元気です。今日は、ソーニャ、貴女と話をしたくてやってきました」
「話、ですか?」
ソーニャは前例のないことに戸惑ってしまいました。
9歳の時に母を亡くしてからかれこれ8年間、ずっと一人で暮らしてきました。
魔女は国の管理下にあるため、毎週日用品・食材が配給されます。
この8年間で話した人といえば、配給を持ってくる人と『魔女の涙』を貰いにくる人だけ。事務的な会話しかありませんでした。
ソーニャの話し相手は、本の中の登場人物、そして、森の動物たちでした。
「ずっと魔女について興味があったんです。この太陽の月(大体8月ごろ)から、森を抜けたところのバーナード領を治めることになりまして。
つい先日王都からやってきたんですが、なにやら近くに魔女が住んでいるというじゃないですか。思わず来てしまいました」
フレンは嬉しそうにアッシュブロンドの瞳を細めています。
一方ソーニャは、ジェイドの瞳をまんまるく広げていました。
魔女に興味がある人など聞いたことがありませんでした。
みんなが興味をもつのは、『魔女の涙』の効果だけだからです。
ソーニャは、胸がとくんと脈打つのを感じました。
なんとも言えないむず痒さがありました。
放っておけば、頬の筋肉が緩みっぱなしになってしまいそうでした。
ソーニャはそれを避けるため、フレンを家の中へ案内します。
「立ち話では申し訳ないので、よろしければ家の中へ」
フレンは、顔を綻ばせながら黙ってソーニャに着いていきました。
3
それからというもの、フレンは度々ソーニャの元を訪れました。
お互い読書家ということもあってか、二人はすぐに無二の親友になりました。
今日もまた、ソーニャの家の扉が叩かれました。
トントン
「どうぞ」
ソーニャは、客人を招き入れました。
「こんにちは、ソーニャ」
毛先が肩ほどのワインレッドの髪を持った青年、フレンでした。
「いらっしゃい、フレン」
身分も越えて友となった二人の間に、もはや敬語も敬称もいりません。
「今日は、異国のファンタジー小説を持ってきたよ」
フレンは、脇に抱えてきた本をソーニャに渡しました。
領主の館の書庫には膨大な数の本がありました。
そこからフレンは、ソーニャが好きそうな本を見繕ってきてくれるのです。
「ありがとう! 待って、部屋から返す本を取ってくるわ」
愛らしい笑顔で本を受けとったソーニャは、小走りで寝室に入っていきました。
シルバーホワイトのお下げ髪が寝室に吸い込まれたところで、家の扉が叩かれました。
トン……トン……
控えめなその音にひとり気がついたフレンは、寝室に引っ込んでしまったソーニャの代わりに扉を開けました。
するとそこには、黒いフードを目深に被った人影がありました。
ローブの裾からはズボンが見えているので、おそらく男性でしょう。
「魔女のソーニャさんですか……」
沈んだ声で男性は尋ねました。
「いや……」
どう答えたものかとフレンが思案している声が漏れると、男性はパッと顔を上げました。
それもそのはず、魔女を訪ねてきたはずが男の声がしたのですから。
「あ、貴方は、領主さま!?」
男性は、顔を上げた先に自分の暮らす地の領主がいたことに度肝を抜かれたようで、口をパクパクさせていました。
「フレン、どうしたの?」
声が聞こえたのでしょうか。寝室から戻ってきたソーニャはフレンに声をかけました。
「あ、ソーニャ」
「お客さま!」
振り返ったフレンの奥に、人影を見つけたソーニャは慌てて玄関に近付きました。
「すみません。私が魔女のソーニャです」
「ああ……魔女のソーニャさん。今日はお願いがあって参りました」
「『魔女の涙』をご所望ですか」
ソーニャの言葉に男は強く頭を振りました。
そして、どうか、どうかと懇求しています。
ソーニャは優しく頷き、「少しお待ちください」と声をかけた後、壁際の棚へと向かいました。
小瓶を手に取ると、顔の下に当てます。
そして、またいつものように思い出すのです。
辛い、悲しい、寂しい……そんな記憶を。
ソーニャが涙を貯めるのを、フレンは黙って見つめていました。
実は、こうやって実際に見るのは初めてのことでした。
あっという間に小瓶に涙が貯まりました。
ソーニャは、袖口で頬を拭いた後、男性に小瓶を渡しました。
「どうぞ。お使いください」
「ああ……ありがとう、ありがとうございます!」
男性は深く頭を下げると、走り去って行きました。
ソーニャは男性が見えなくなるまで見送った後、家の扉を閉めました。
そして振り返り、フレンにおやつにクッキーでもどう? と言おうとしましたが、それはかないませんでした。
大きな体に、すっぽりと覆われてしまったからです。
背に回る腕の強さに、額に感じる胸の鼓動に、体全体に伝わる温かさに、ソーニャは顔を真っ赤にしてしまいました。
幸い、相手にそれは見えていませんでしたが、落ち着かないことには変わりありません。
「フ、フレン」
ソーニャは上ずった声で、フレンの名を呼びました。
ぎゅっと腕の力が増した後、頭上から低い、けれども澄んだ声が聞こえました。
「いつもああやって泣いてたの?」
「ああやって?」
フレンの静かな声が耳に響きます。
「ああやって……辛そうに、悲しそうに」
ますます腕に力が込められ、少し息苦しくなりました。
ソーニャがトントンとフレンの腕を叩いて訴えると、ようやく離してくれました。
見上げると、なぜかフレンの方が苦しそうな、泣きそうな顔をしていました。
「どうして貴方がそんな顔をするの?」
ソーニャは、そっとフレンの頬に指を当てました。
フレンは、アッシュゴールドの瞳を揺らしたまま、ソーニャの問いかけには答えてくれません。
「涙を流すのだから、辛くて当たり前よ。悲しいから泣くんだもの」
「……ソーニャは悲しい以外の感情で泣いたことはないのかい?」
ようやく口を開いたフレンは、自分の頬にあるソーニャの手を取り尋ねました。
ソーニャは考えます。
悲しい以外の感情――嬉しい・悔しい・腹立たしい・楽しい・幸せ。
小説の中では、主人公たちが様々な感情をともなって涙を流していました。
けれども、ソーニャが知っているのは悲しい涙だけでした。
ゆっくり頭を横に振り、ソーニャは返事をしました。
「ないわ」
ソーニャの返事を聞いたフレンは、ソーニャの手を掴んだまま、家の外へ走り出しました。
手を引っ張られ強制的に走らされるソーニャ。こけないように、必死に足を動かすほか術がありません。
「どこへ行くの!?」
森の道を走り抜けてゆく二人。
息も絶え絶えながら、ソーニャはフレンに問いかけます。
すると、フレンは振り返り、答えました。
「バーナードへ行こう!」
4
あと少しで森を抜ける、というところで、ソーニャの中に不安が押し寄せました。
実は、お母さんを亡くした8年前から、一度も森を出たことがなかったのです。
ソーニャの母・ミーシャが生きていた頃は、二人でバーナード領から少し離れた街で暮らしていました。
ミーシャは、配給を施しを受けるようだと嫌い、花屋を営んでいました。
小さな店でしたが、それなりに繁盛していました。
ソーニャは、母が仕事の間は外で時間を潰していました。たいてい、近所の広場で花冠を作ったり、蟻の行列を眺めたりして過ごしていました。
しかし、時折、ソーニャに話しかけてくる子どもたちがいました。
いや、話しかけるという言葉は適切ではありません。
子どもというのは正直で、素直で、時に残酷です。
魔女を象徴するシルバーホワイトの髪とジェイドの瞳を理由に、ちょっかいを出してくるのです。
なんで、そんな変な色をしているのか。
動物と話せるなんて嘘つきだ。
涙で病気を治せるなんて、人間じゃない。
まだ善悪の区別が曖昧な子どもたちは、言葉を飲み込むことを知りませんでした。
ミーシャが亡くなり、ソーニャは国の保護を得て、今の森に移り住みました。
それからは、もう皆さまもご存知の通り……フレンが現れるまで他愛もない会話をする相手すらいませんでした。
ソーニャにとって、外の人がすっかりトラウマになっていました。
涙を貰いにくる人は、自分を頼りに来ている人だから怖くはありません。
けれども、普通の人々が、自分を見て、魔女を見てどう思うのかが、ソーニャは怖くて堪たまらなかったのです。
フレンは、繋いだ手が震えていることに気が付きました。
振り向くと、少女の顔は真っ青でした。
「どうしたんだい、ソーニャ」
立ち止まったフレンは、ソーニャに問いかけます。
ソーニャは、ひどく憂鬱な顔で答えました。
「外が怖い……人が怖い」
フレンは、きょとんとしました。先ほど、人と接する彼女を見て、とてもそんなふうには見えなかったからです。
そしてなにより、フレンだけが知っている事実がありました。
「大丈夫だから、ついておいで」
フレンは優しく笑いかけると、再びソーニャの手を引いて歩きはじめました。
ソーニャは、胸に不安を残したまま、信用できる彼の背中を追いました。
5
森を抜け、街道を歩いていると、一人の少年が二人に近づいて来ました。
「領主さま!」
「おや。キース、ちょうどいいところにきたね」
少年・キースのゴールドの髪を撫でたフレンは、彼をソーニャの前に立たせました。
「このお姉ちゃんは?」
キースは、フレンを見上げながら尋ねます。
「キースを助けてくれたソーニャだよ」
「え!? あなたが魔女さま!?」
キースは、目をキラキラさせながらソーニャのジェイドの瞳を見つめました。
少年を見て、幼きころの記憶が蘇るソーニャの表情は固いものでしたが、少年から悪意は感じません。
ソーニャは、ごくりと生唾を飲み込むと、少年に答えました。
「はい。魔女のソーニャです」
すると、腰を少しかがめ話しかけたソーニャの手を、キースはがしっと掴みました。
小さい、温かい手でした。
「ぼく、『魔女の涙』で病気が治ったんだよ! もう家で寝てなくてよくなったんだよ! ありがとう!!」
満面の笑みでお礼を告げるキースを、ソーニャはぽかんとした表情で見ていました。
涙をあげた人は数え切れません。しかし、お礼を言われたのは初めてだったのです。
「キースは、僕が初めてソーニャに会いに行った日にきていた女性、彼女の息子だよ」
フレンは、キースの肩に手を置きながら言いました。
フレンが言った日のことはよく覚えていました。初めての友達と初めて会った日ですから。忘れられるはずがありませんでした。
「あの時の……」
たしかに女性は、息子が病気だと言っていました。
ソーニャは、胸をきゅっと掴まれるような感覚をもちました。
「魔女さま! 街に来て! お母さんにも会って! それから、ゴーダおじさんとアリスおばさんとナッシュとケリーと……えっとえっと、とにかくたくさん! みんな魔女さまにお礼を言いたいと思ってるんだよ!」
キースは、ソーニャの腕を引っ張りました。
ソーニャは、戸惑いながらもキースに着いていきました。
街では、領主であるフレンに気が付いた人々が集まってきます。
そして、人々の視線は彼の連れのソーニャにも向けられました。
「あれは、魔女!?」
ソーニャの色に気が付いた人の言葉が、彼女の耳に入りました。
ソーニャは身を固くします。
けれども、何も怖がることはありませんでした。
みんな、先ほどのキースと同様に、いえ、それ以上に、次々に絶え間なくソーニャへお礼を伝えました。
「魔女のソーニャさん。その節はありがとうございました! おかげさまで妻は今でも健康です」
「本当にありがとうございます! お陰様で、母は寿命いっぱい生きることができました」
「ありがとうございます!」
「ありがとう、ソーニャさん!」
みんな笑っていました。
幼きころ見た意地悪な、歪な笑顔ではありません。
心から感謝の気持ちを持った人の笑顔でした。
ジェイドの瞳から、雫が垂れおちました。
とめどなく溢れ、頬に痕を残していきます。
鼻も目も真っ赤になってしまいました。
「魔女さま、どこか痛いの?」
「魔女さま、悲しいの?」
子どもたちが心配そうに顔を覗のぞき込みます。
ソーニャは、首を横に振りました。
言葉は音になりません。
この涙が、いつもの塩辛いものとは違うことに、ソーニャは気づいていました。
いつもは胸がズキズキと痛むのに、ぽっかりと虚しさが襲うのに……今はどうでしょう。
胸はきゅっと音を鳴らし、心地よい痺れを感じます。虚しさはおろか、ぽかぽかしたもので満たされていました。
「それが嬉し泣きだよ」
ソーニャの後ろから声がしました。
フレンのものでした。
「嬉し泣き……」
ソーニャは、初めて悲しみ以外の感情で泣いたのです。
塩辛いのも、目が熱く火照るのも、鼻がツンと痛むのも、いつもと変わりません。
けれども、”嬉し泣き”というのは、とても心地よいものでした。
幸せでした。
「フレン。わたし、間違っていたわ。外の人が怖いって決めつけたりしないで、きちんと向き合えばよかった。そうすれば、嬉しい涙も、もっと早く知れたかもしれない」
「そうだね。ひとりで知ることのできる感情は少ないよ。たとえ失敗しても怖がらずに向き合っていかなきゃね。ソーニャならきっとできるよ」
フレンの優しい言葉に、ソーニャは笑みを浮かべました。
それは、まっ白な積雪からひょっこりと顔を出した雪中花のような、可憐なものでした。
フレンは、にっと口角を上げると、ソーニャを引き寄せ自分の胸におさめました。
そして、嬉しそうに言うのです。
「ソーニャ。僕がこれからも色んな感情を君にあげる。どうか僕の隣で生きてほしい」
フレンの突然の申し出に、街人の歓声が上がりました。
その声にかき消されてか、ソーニャの返事は聞こえませんでしたが、フレンの背中に回された手を見れば……お分かりですね。
◆◆◆
大陸の西、国境の半分が海に面した小国・アルカンドラ王国には、ある噂がありました。
『魔女の涙は、百薬の長
どんな病も、たちどころに治る』
ある人にとっては、絵空事。
ある人にとっては、最後の頼みの綱。
そして、バーナード領の民にとっては、嘘偽りのない真実でした。
領主フレン・ナシャータ・エルカ・アルカンドラの治世下において、バーナード領の民はみな健やかに暮らしました。
領主の隣にはいつも、シルバーホワイトの髪の女性がいたといいます。